本文
おもに市民が行うための一次救命処置(心肺蘇生法など)
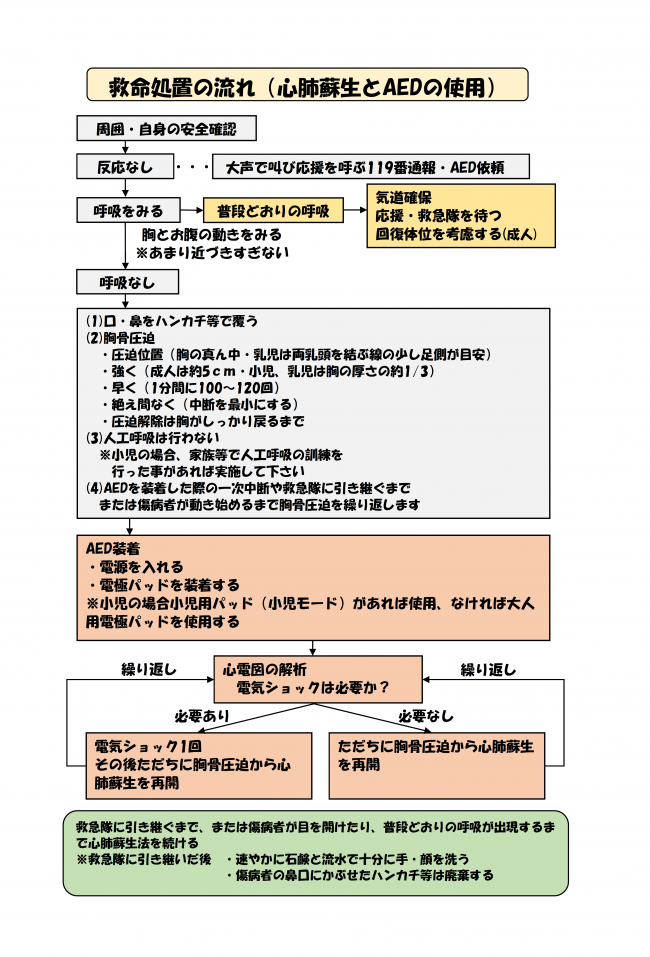
周囲・自身の安全の確認
倒れている人に近づく前に周囲を見渡して、安全かどうかを確認する。
反応を確認する
反応がなければ・・
- 大声で叫んで周りの人に助けを求める。
- 「あなたは119番通報をしてください。」「あなたはAEDを持ってきてください。」と具体的に指示する。
呼吸の確認(=心停止の確認)
倒れている人が「普段どおりの呼吸」をしているか胸とお腹の動きを見て10秒以内で確認します。胸とお腹の動きを見るときはあまり近づきすぎない。
普段どおりの息をしている
回復体位にして様子を見守りながら救急隊の到着を待ちます。
普段どおりの息をしていない
心肺蘇生法へ
心肺蘇生法
(1)口・鼻をハンカチ等で覆う。
(2)胸骨圧迫
・圧迫位置(胸の真ん中・乳児は両乳頭を結ぶ線の少し足側が目安)
・圧迫は強く(傷病者の胸が約5cm沈むまで)
・速く(1分間に100回から120回)
・絶え間なく(中断を最小にする)
・圧迫解除は胸がしっかり戻るまで
(3)人工呼吸は行わない。
※小児の場合、家族等で人工呼吸の訓練を行った事があれば実施して下さい。
(4)AEDを装着した際の一次中断や救急隊に引き継ぐまで、または傷病者が動き始めるまで
胸骨圧迫を繰り返します。
AED装着
(1)AEDによる心電図解析
AEDが患者の心電図を調べて、心臓に対して除細動(電気ショック)が必要か否かを
判断します。
電気ショックが必要な場合(AED)
電気ショック1回、その後、直ちに胸骨圧迫を再開し、2分間行います。
2分後にAEDが再び解析を行います
電気ショックが必要ない場合(AED)
直ちに胸骨圧迫を再開し、2分間行います。
2分後にAEDが再び解析を行います。















