本文
いきいき学びのプラン(55号)
いきいき学びのプラン第55号 平成27年(2015)9月号
2015年9月55号 一括ダウンロードはこちら [PDFファイル/5.66MB]
1面 ひとが咲く。 堀野和人さん / 中年の星 [PDFファイル/1.82MB]
2-3面 放課後子ども教室 学校支援地域本部 親学習リーダー [PDFファイル/2.87MB]
4面 動き出してます!学び舎プログラム まちづくり実践プロジェクト [PDFファイル/1.8MB]
1面 ひとが咲く。 中年の星
ひとが咲く。堀野和人(かずと)さん
公民館の定期講座で講師をしている堀野和人さん。一級建築士の資格を持ち、事務所を開くかたわら、公民館や地域での活動も積極的に行っています。仕事と地域の活動にかける思いを聞いてみました。

堀野和人(ほりのかずと)さん
堀野さんの主な活動
●一級建築士事務所 スマイリズム.代表
●公民館講師
●特定非営利活動法人神於山保全くらぶ会員
●岸和田文化事業協会広報部会理事
●岸ぶらがー(岸和田市観光振興協会公式サイト認定ライター)
●岸和田市都市計画審議会公募委員
お仕事は?
住宅を中心とした建築設計の仕事で自称ハウジングプランナーです。
新築やリフォームの計画を納得いくよう進めるための間取りの提案やアドバイスを通して、良い住まいづくりのお手伝いをしています。また、自分の思いや経験を多くの方に伝えるために、住まいづくりに関する講座や本の執筆も進めています。
公民館に来るようになったきっかけ
サラリーマンを辞めたことですね。
それまで土日は最も忙しい曜日だったのが結構自由になりました。たまたまそのタイミングで公民館講座が目にとまり、受講したのが公民館活動のスタートです。「地元のこと、こんなに知らんねんや」と驚き、素敵な講師と講座仲間にも出会えました。
それまでは地域活動に主体的に参加したことはありませんでした。ただ私が子どもの頃、父が中央商店街(現かじやまち)で商店を営んでおり、町会やPTAなどの地域活動に積極的に参加していた様子はよく見ていました。抵抗なく公民館活動を始められたのは、そんな父の影響もあると感じています。

仕事場での様子
活動の動機、今後の目標は?
地域に対してお返しをしたい気持ちが一番ですね。そう思うようになったのも父の存在が大きいと思います。今でも友達から「ソフトボールを教えてもらった」「キャンプに連れて行ってもらった」などの思い出話を聞くことがあります。やはり似てくるのでしょうか。自分も何か残してあげたいと思い始めました。それもリタイアしてからではなく、現役世代の間に。
義務感でやっていることは一つもありません。楽しさがないと活動は続かないものです。地域での活動が人とのつながりを広げ、そのつながりがさらに新たな活動へと広がっていきます。
将来的には、専門的な知識や技術を伝えるだけでなく、人と人とをつないでいく役割を担えるようになりたいと思っています。
これから地域活動をはじめる人へ
初めて行くところは誰でも緊張します。実は私もあまり得意ではありませんが、まずは続けてみることですね。その先に新たな世界が広がることを信じて―笑。
友達やご家族で。または、私のように子どもをダシにつかってじんわりと浸透していくのも良し。是非、勇気と好奇心をたずさえて、その一歩を踏み出してください。

お子さんと参加している神於山保全くらぶの活動で竹割りを指導

市立公民館「住まいづくり講座」
話をお伺いしている間も終始飄々(ひょうひょう)とした雰囲気の堀野さんでした。この軽やかさが色々な活動を続けていく秘訣かもしれません。
中年の星
今年の7月23日、ソユーズ宇宙船が油井亀美也(ゆい きみや)さんを乗せ国際宇宙ステーション(ISS)に向けて打ち上げられた。ニュース番組でそれを知った私には「中年の星」という言葉がとても心に残った。中年の領域、概ね40歳まで達しても活躍を続ける人のことをそう言うらしい。
油井さんは歴代最年長の39歳で宇宙航空研究開発機構(JAXA)の宇宙飛行士候補者に選ばれた。そして、45歳で国際宇宙ステーションへ。まさしく中年の星である。
宇宙飛行士という仕事は精神的、特に肉体的にキツイ仕事のように思う。映像を見ているだけでも落ち着かない無重力。その中での5ヶ月間は想像しがたい。長い間訓練をし、たくさんのテストをパスした油井さんを私が心配する必要はないが、45歳の体にどれだけの負担か。
小学校の卒業文集に「勉強して20年後には火星に行っている」と夢を綴った油井さん。防衛大学校を卒業し、パイロットとして航空自衛隊に所属していたが、ずっと宇宙飛行士への夢、憧れを持ち続けていたのだという。
なんと500倍の難関を突破して宇宙飛行士候補者になったのだ。
中年の星が輝いている。
2面-3面 子どもの笑顔で地域も元気に 地域の子どもを地域で育てよう‼
2面 放課後子ども教室
- 安心・安全な子どもの居場所
- 市内9カ所で実施
放課後子ども教室は、放課後や週末などに、子どもが安心して活動できる場所です。地域のボランティアの方々の参画や協力を得て、子どもたちが、スポーツ・文化活動などさまざまな体験活動をおこなっています。
・実施回数や実施時間は、教室によって異なります。
・教室によっては、普段の活動に加え、夏休みなどの長期休暇中も活動しています。
平成27年度 岸和田市放課後子ども教室一覧
- てんてん天神山子ども教室
- 場所:天神山小学校
曜日:水曜日
内容:おはなし会、工作など - ゆうゆう大宮
場所:大宮小学校
曜日:水曜日
内容:工作、映画鑑賞、校外学習、クッキング、陶芸など - 中央子ども教室
場所:中央小学校
曜日:水曜日
内容:スポーツ、茶道、書道、図工(クラブ制) - 城北公民館スクール
場所:城北地区公民館
曜日:土曜日
内容:卓球、バドミントン、読書、ボール遊び、プールなど - 大芝あそびクラブ
場所:大芝小学校
曜日:水曜日
内容:太鼓演奏、昔あそび、卓球、お楽しみ会など - 学びの教室春木
場所:春木小学校
曜日:水曜日
内容:国語クイズ、工作、読書、校外学習、自由遊びなど - 八木っ子クラブ
場所:八木小学校
曜日:土曜日
内容:卓球、バドミントン、工作、折り紙、ボール遊びなど - 修斉放課後子ども教室
場所:修斉小学校
曜日:水曜日
内容:野菜の収穫、工作、紙芝居、昔あそび、校外学習など - わくわく教室山北
場所:山直北小学校
曜日:水曜日、土曜日
内容:ドッジボール、ソフトボール、習字体験、絵画など
Q&A
- Q.子どもを参加させたい!申込方法や対象は?
A.年度初めに、募集をおこないます。(学校を通じて、チラシを配布します。)
対象は、校区内の小学生です。(対象学年は、教室によって異なります。) - Q.子どもたちのために、ボランティアとして参加したい!
A.生涯学習課にご相談ください。ご希望に応じた子ども教室をご紹介します。 - Q.自分たちの校区でも放課後子ども教室を立ち上げたい!どうしたらいいの?
A.まずは、生涯学習課にご相談ください。内容や場所や方法など、一緒に知恵をしぼりましょう。

親子で対決!ボールリレー♪

太鼓の演奏♪
人のつながり 地域のつながり 放課後子ども教室・学校支援地域本部・親学習リーダー
主催:岸和田市教育委員会
問合せ:生涯学習課(市立公民館内)
電話:423-9616(月曜日・祝日は休館)
3面 学校支援地域本部・親学習リーダー
学校支援地域本部 地域による学校の応援団!市内11カ所で実施
学校支援地域本部は、地域につくられた学校の応援団です。
全中学校区にあり、学校の求めと地域の力をマッチングします。
さまざまな場面で、学校を支援し子どもたちの育ちを支えます。
学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで子どもを育てます。
- 中学校区を中心に活動しています
- 学校支援コーディネーターは学校と地域を結びます
地域 家庭・町会・PTAなど
学校支援コーディネーター
各学校支援地域本部に1名から数名が配置され、学校の「こんなことできないか」と地域の「こんなことできるよ」をつなげて、地域の子どもたちを地域で育てることを目指して活動しています。
学校 生徒・先生 支援、協力依頼
「こんな活動をしてほしい!」や「お手伝いしてほしい!」などの要望を地域の方々に出して、協力・サポートをお願いします。
学校支援活動・サポート
活動の例
●あいさつ運動
●学習支援
●学校内外の美化活動
●花と緑のボランティア
●図書活動・読み聞かせ
学校支援ボランティア募集
農業や林業の体験、華道やパッチワークなど、さまざまな活動を通して学校を支
援するボランティアを募集しています。
特別な知識や技能がなくても大丈夫です。何かお手伝いしてあげようかと思っていただける方、大募集!
お知らせ
10月のテレビ岸和田に「学校支援地域本部」が登場します!
興味のある方は、チェックしてみてください♪
市ホームページにも、各中学校の紹介が載っています、検索はこちら。岸和田市 応援団

親学習リーダー
親学習リーダー 「親」をまなぶ・「親」をつたえる
親学習は、保護者同士がお話や交流を通して行う、親子の関係や子育てについての学び合いです。この親学習の進行役となるのが「親学習リーダー」です。
岸和田では、親学習リーダー会「はっぴねす」が交流や講座などのお手伝いをしています。
- 親学習リーダー会「はっぴねす」
大阪府の親学習リーダー養成講座を受講し、岸和田で親学習リーダーとして活動するグループです。

親学習のルールを説明する「はっぴねす」のメンバー

グループワークの様子
学校支援地域本部でも活動
土生中学校の学校支援地域本部では、親学習リーダー会「はっぴねす」が進行役となって乳幼児とその保護者が参加し生徒と交流しました。乳幼児とふれあうことで、命や愛情の大切さに気づく機会となりました。

赤ちゃんとのふれあい
ちょっと予告
親学習ステップアップ研修会♪
講師 津村 薫さん 女性ライフサイクル研究所フェリアン(副所長)
テーマ 「女性の可能性に気づく~心理学的タイプ論を支援に活かす~」
日時 10月21日水曜日 午前10時から午後3時15分まで
場所 市立公民館(堺町)
※10月号の広報きしわだで募集‼
4面 動き出しています!学び舎(まなびや)プログラム
まちづくり実践プロジェクト
「学び」を活かしたまちづくりの取り組みを、市民が企画・提案して実施する「まちづくり実践プロジェクト」は今年度スタートした新しい事業です。初のプレゼンテーションには、8グループが応募し、それぞれがまちづくりへの思いを込めた提案を発表しました。
選考の結果、5グループの企画が委託事業として実施されることになりました。そのグループと企画についてご紹介します。
(各事業については随時 広報きしわだ で参加者を募集しております)
ハーベスト・コールきしわだ 60歳から楽しむ歌の世界
60歳以上の男性が集まって、歌うことを通して趣味づくり、仲間づくりができる場を企画しました。
「ハーベスト」は「収獲」という意味の言葉。私もぼつぼつ人生の収獲期に入ったかなという思いで、グループ名に取り入れました。
初心者歓迎の男性限定で参加者を募集します。男性が活動できる場のすそ野を広げて、元気な男性グループが増えるきっかけにしたい。仕事をリタイアしてから、趣味が見つからない男性はたくさんおられるのでは?そんな人にぜひ来てほしいです。
日本の美しい童謡や唱歌、歌謡などを歌いながら、ハーモニーさせたり、声の出し方や楽譜の読み方、その曲の背景などを学んでいく・・・。
歌を通じて文化にも親しみながら、ここを出発点に、参加者がそれぞれ新たな方向に踏み出して行けたらよいと思います。

代表 岡崎さん
NPO法人 自立生活センター・いこらー 障害者発☆防災力アップセミナー
「いこらー」では、どんな障害があっても地域で当たり前に生活することを目的にヘルパー派遣や、生活の相談に応じたり、地域の方とさまざまな取り組みをしています。
今回の企画のひとつには、ひとり暮らしの障害者の自宅を公開して、障害者が大震災に遭ったという想定で行うシミュレーションを取り入れています。
障害者福祉に普段は関わることのない人と一緒に実施したいです。防災士や、東日本大震災のボランティアに行かれた方の意見も取り入れ、よりリアルなものにしたいと考えています。
障害のない人でも、大けがをしたり避難所で病気になったりすれば、助けが必要な立場になると思います。
「震災弱者」の目線で、障害者自らが大震災に備え、防災について考えて情報を発信していきたいと思っています。

理事 喜多田さん
ボランティアグループ友垣(ともがき) むぎのほとむぎちゃ
社会福祉協議会に登録している2つのボランティアグループ「友垣」と「麦踏みファンズ」が共同で講座を企画しました。
「友垣」は手縫いを中心とした幅広い「手作り」活動をしながら、ひきこもりの若者との交流や、被災地大船渡市の仮設住宅に手作りキットを贈る支援などもしています。
「麦踏みファンズ」は、麦を通して自然環境を考えるほか、種を蒔まいて育てた麦を使って蛍籠(ほたるかご)などの麦わら細工やお菓子などを作る活動もしています。
今回は「友垣」が布とワイヤーを使った麦のクラフトを参加者と一緒に作り「麦踏みファンズ」が麦を切り口に自然と環境についてのお話をします。
家族で参加して、岸和田育ちの麦を使った麦茶を飲みながら、楽しく学んでいただきたいです。
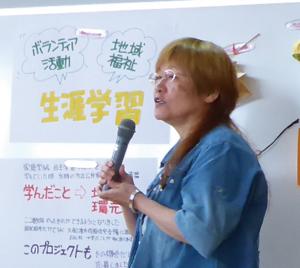
代表 稲富さん
生活廃棄物有効利用研究会 虹の環(にじのわ) 楽しく、おもしろい、やってみたい環境学習
「虹の環」は「ごみになる前に再利用を」を合言葉に、3R(※)の知恵と工夫を地域に広げる活動をしています。例えば、環境イベントなどで不用品を使ったおもちゃ作りの指導をすることもあります。
今回は、身近な環境問題を軸にして講座を考えました。
日常生活から出た不用品を再利用したクラフトや、買い物から環境を考える 体験ゲーム、地球温暖化防止や省エネ・ごみの減らし方などについての講演など、8つの講座を企画しています。
物のない時代に育った世代の知恵をプログラムの随所に活かしています。楽しみながら環境の大切さを感じ取っていただきたいです。
※3Rアール
Reduce:リデュース(減量)
Reuse :リユース (再利用)
Recycle:リサイクル(再資源化)

代表 竹中さん
NPO法人ここからKit(キット) あなたの声が聴きたくて~心の声に耳を傾ける~
子どもや、子育てに関わる大人の居場所づくりなどをしている団体です。今回は、児童虐待を防ぐために、虐待をしてしまう大人の心を助けたいと「子育て傾聴」への取り組みを考えました。
「子育て傾聴」とは、子育ての悩みに寄り添い聴くこと。行き詰まっている時、誰かにそうしてもらうことで、ひとりぼっちではないことや、子育ての楽しさを実感し、自信を取り戻すことができるのではないでしょうか。それを通して自己肯定感を回復してもらいたいと思います。
「子育て支援傾聴ボランティア養成講座」を全5回行います。今の子育て世代の心理や悩みとともに、岸和田市の子育て支援の現状にも触れ、傾聴の心構えから方法までを学べる講座にしたいです。

代表理事 長谷川さん














